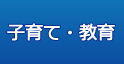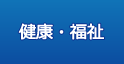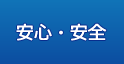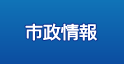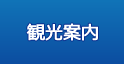武田耕雲斎等墓、水戸烈士記念館(旧鯡蔵)の整備が完了しました
最終更新日:2025年1月17日
武田耕雲斎等墓、水戸烈士記念館(旧鯡蔵)の周辺整備が完了しました。
ガイダンス施設は令和6年10月11日(金曜)より公開しています。(旧鯡蔵は通常は外観のみの見学です。)
水戸烈士記念館(旧鯡蔵)について
水戸烈士記念館(旧鯡蔵)の沿革
水戸烈士記念館(旧鯡蔵)は、元治2年(1865年)に敦賀で降伏した水戸天狗党の浪士823名を収容した船町(現蓬莱町)に所在した荷蔵16棟の内の1棟です。戦後、敦賀港修築工事で撤去が計画されていましたが、保存を希望する地域住民の運動を受け、昭和29年(1954年)に「水戸烈士記念館」として松原神社境内に移築されました。
この建物は、水戸天狗党の浪士が収容された歴史と、それを保存しようとした市民運動を物語るものであるとともに敦賀市に唯一残る近世期敦賀港の倉庫であることから、地域を理解する上で有益であり、きわめて貴重なものとして、令和2年11月6日に有形文化財(建造物)として敦賀市指定文化財の指定を受けました。
令和3年から令和5年にかけて移築・修復工事が行われ、現在の位置に移っています。
建物の特徴
水戸烈士記念館(旧鯡蔵)は、南北(梁行)3間(5.46m)、東西(桁行)11間(20.72m)の矩形平面で、東から4間、2間、2間、3間の4つの蔵状の建物を元にした改修が施されており、長大な構造を有しています。
また、ほぼ全ての柱や梁に継木が施されており、長年に渡って各部材が転用されていることがわかります。また、棟札には、「寛文一〇年」と記されていることから、少なくとも江戸時代から倉庫として利用されてきたことがわかります。

外観

内観

棟札表面

棟札背面
水戸天狗党浪士収容時の様子
荷蔵16棟に収容された浪士たちは厳しい環境に置かれます。浪士を幕府軍に引き渡した加賀藩の記録では、入り口は小さな器が通るほどしか開いておらず、その他の窓は板で打ち付けられていました。蔵の内部はむしろが敷いてあるだけで、中央に便所桶が置いてあったとされています。また、浪士には釘で打ち付けられた木の足枷がはめられ、1日の食事は握飯が2度ほど与えられるだけであったと記録されています。

「水府正士濱荷蔵へ入図」(『天狗党騒動図』明治時代、敦賀市立博物館蔵)
文化財の基本情報
指定名称 |
水戸烈士記念館(旧鯡蔵) 1棟 |
|---|---|
所在地及び管理者 |
敦賀市松原町 敦賀市 |
時代 |
建立 寛文10年(1670年) |
構造 |
木造平屋建切妻造桟瓦葺 |
規模 |
桁行(東西) 20.72メートル |