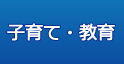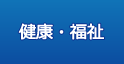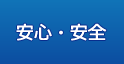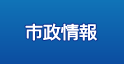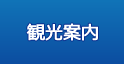金ヶ辻子山車水引幕復元新調完成披露式
最終更新日:2015年3月1日
水引幕の復元新調完成披露会

水引幕披露

復元新調された水引幕
金ヶ辻子山車水引幕復元新調完成披露式
6月17日(日曜日)にみなとつるが山車会館において、復元新調された水引幕(2面)の完成披露式を行いました。
敦賀まつりの華とも言える6基の山車は、うち3基が敦賀市の文化財に指定されています。
この指定文化財である3基の山車の水引幕は江戸時代から引き継がれてきたとも言われる大変貴重な文化財ですが、経年による劣化が著しいため、文化財保護の観点からも、これらの幕は歴史資料として大切に保存することとし、平成19年度より復元新調が行われています。
先に完成披露した御所辻子山車(4面)、唐仁橋山車(4面)に続き、
平成23年度に完成した【金ヶ辻子山車の水引幕2面】が披露されました。
【金ヶ辻子山車(かねがずしやま)】昭和46年市指定文化財
山車の多くは戦災で失われてしまいましたが、わずかに焼失を免れたうちの1つが金ヶ辻子山車でした。しかし、金ヶ辻子山車の管理が困難になり、売却、散逸に直面した際、大金区出身の大塚末子氏により金ヶ辻子山車一式の購入がなされ、昭和45年に敦賀市へ寄附いただきました。こうして山車を一体のまま保存することが可能になり、翌年に敦賀市の文化財に指定されました。
【水引幕(埒幕:らちまく)】
金ヶ辻子山車の水引幕(埒幕)には『中国故事図』が描かれています。
今回修復した2面の水引幕は、西王母(せいおうぼ)にまつわる逸話を描いたものと見られます。西王母とは中国の伝統的な民衆宗教である道教で信仰される仙人のことです。
神々が集まるとされる崑崙山(こんろんさん)に住み、庭には3000年に一度実をつけ、食べると不老長寿になるという「蟠桃(ばんとう)」の樹があり、桃や頭にそなえた勝(しょう)(髪飾り)が西王母の象徴となっています。不老長生をつかさどる仙人として知られ、多くの説話が伝えられています。また、吉祥の画題として好まれる題材の一つです。
左側面の水引幕は中国の皇帝の政治を描いた帝鑑図とよく似た構図をとっていて、中国古代の皇帝にまつわるエピソードを持つ西王母の存在を暗示させます。この水引幕とほぼ同様の図像が宵宮山車の水引幕にも描かれていて、互いの水引幕に関連があることが窺われます。
後面の水引幕には、飛翔する女性と地上の男性が対面する場面が描かれています。西王母には、地上の人物と会合する伝承も残されていることから、本図も西王母にまつわる図案であると見られます。
「金ヶ辻子山車」と復元新調された水引幕は現在、
みなとつるが山車会館で実際にご覧いただけます。
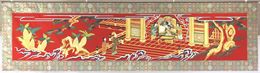
左側面

後面

新調された大谷吉継像の面

古木庵 能面師 桑田能忍氏(池田町能面美術館前館長)より寄贈