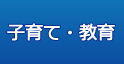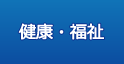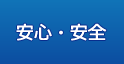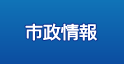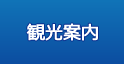医療費が高額になったとき
最終更新日:2025年7月24日
高額療養費
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方と70歳以上の方では、限度額が異なります。
70歳未満の方の限度額
| 所得要件 | 支給回数が3回目まで | 4回目以降 (注1) |
|---|---|---|
旧ただし書所得 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
旧ただし書所得 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
旧ただし書所得 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
旧ただし書所得 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注1)該当月を含む過去12か月以内に、同一世帯で限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
(注2)多数回該当は同一保険者での療養に適用されます。全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合などから国民健康保険に加入した場合など、保険者が変わったときは多数回該当の月数に通算されません。
(注3)「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除額(43万円)を差し引いた額をいいます。同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者の所得の申告がない場合、901万円超とみなされます。
自己負担額の計算方法
70歳未満の方の高額療養費については、高額療養費の対象となる要件があり、以下の計算で21,000円以上になるものだけを合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
- 月ごとの計算(月の1日から月末まで)
- 医療機関ごとで別計算
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
- 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
- 入院した時の食事代や差額ベット代、保険診療外分は対象外
- 保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したものに限る)と医療機関の診療費は合算
70歳以上の方の限度額
| 所得区分 | 所得要件 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 |
|---|---|---|---|
現役並み所得3 |
課税所得 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得2 |
課税所得 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% |
|
現役並み所得1 |
課税所得 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% |
|
一般 |
課税所得 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得2 |
住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
住民税非課税 |
8,000円 |
15,000円 |
(注1)該当月を含む過去12か月以内に、同一世帯で限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
(注2)多数回該当は同一保険者での療養に適用されます。全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合などから国民健康保険に加入した場合など、保険者が変わったときは多数回該当の月数に通算されません。
- 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。(1日生まれを除く)
70歳以上の方の所得区分判定基準
70歳到達月の翌月1日から適用されます。(誕生日が1日の方は当日から適用されます。)
| 所得区分 | 負担割合 | 判定基準 |
|---|---|---|
現役並み所得3 |
3割 (注1) |
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の国民健康保険の被保険者がいる方。 |
現役並み所得2 |
3割 (注1) |
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳以上の国民健康保険の被保険者がいる方。 |
現役並み所得1 |
3割 (注1) |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国民健康保険の被保険者がいる方。 |
一般 |
2割 |
現役並み所得1、2、3および低所得1、2に該当しない方。 |
低所得2 |
2割 |
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方(「低所得者1」以外の方)。 |
低所得1 |
2割 |
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 |
(注1)70歳以上の国民健康保険被保険者の収入額が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合は、「一般」の区分になり、2割負担になります。所得が確認できない場合は申請が必要です。
高額療養費支給申請手続きに必要なもの
- 申請書(自己負担額が高額になり、申請が必要な方には、診療月の約3か月後から4か月後に国保年金課から申請書が送付されます。申請書がご自宅に届いてから、手続きにお越しください。)
- 該当診療月の医療費の領収証
- 預金通帳
- 世帯主および申請書にお名前の記載がある方のマイナンバーが分かるもの
- 身分証明書
(注)診療月の翌月1日から2年を経過すると、高額療養費の申請・請求ができませんので、ご注意ください。(権利の消滅時効)
自動償還を希望の場合は申請が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証について
医療機関で診療を受ける際、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口で提示することにより、医療機関で支払う自己負担額を、限度額に抑えることができます。
申請の仕方についてはこちらをご覧ください。
限度額適用認定証(高額な医療費の支払いを限度額までに抑えたい場合)
高額療養費貸付制度
高額療養費の支給対象に該当する場合で、医療機関への支払いが困難な場合は、高額療養費の9割以内での貸付制度があります。
詳しくは国保年金課までお問い合わせください。