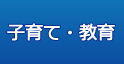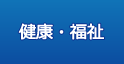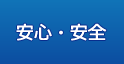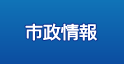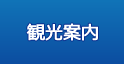固定資産税
最終更新日:2023年2月9日
固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格を基に税額が算定されます。
固定資産の価格は3年毎に見直し(評価替え)を行い、原則として基準年度の価格を翌年度・翌々年度にも据え置きますが、地目の変換、家屋の損壊等があった場合は修正後の価格で算定されます。
地価の下落傾向により、価格が下落した土地は平成10年度から、基準年度以外の年度でも価格が修正されるようになりました。
毎年4月にお届けする納税通知書に、課税対象の土地・家屋を明示した課税明細を綴っておりますので、ご確認いただき、大切に保管してください。
納税義務者
賦課期日(1月1日)現在で、敦賀市内に所在する固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が納税義務者となります。
固定資産税には月割の制度がないため、1月2日以降に所有者を変更した場合においても納税義務者は変わりません。
また、1月2日以降に家屋を取り壊した場合等は、当該年度に限り課税されます。
非課税制度
人的非課税
- 国や地方公共団体等が所有する固定資産
用途非課税
- 宗教法人が本来の用途で使用する境内建物及び境内地
- 学校法人等が設置する学校で、直接教育又は保育の用途で使用する固定資産
- 公共の用に供する道路 等
税 率
標準税率の1.4%を採用しております。
免税点
市内において、同一の名義人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額のそれぞれの合計額が次の額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
納期
固定資産税の納期は、4月、7月、12月、2月の年4回です。
固定資産税額の算出方法
課税標準額×税率1.4%=固定資産税額
土地に対する課税
地目別に、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて1筆ごとに評価します。
原則として課税標準額は評価額と同額になりますが、住宅用地に係る特例や負担調整措置などを適用する場合は、課税標準額が評価額よりも低くなります。
住宅用地に係る特例による軽減
住宅として人が日常生活で使用する区画された敷地を住宅用地と言い、住宅の床面積の10倍を限度として、課税の特例が適用されます。
- 住宅1戸につき200平方メートルまでは、課税標準額が6分の1になります。
- 住宅1戸につき200平方メートルを超える部分は、課税標準額が3分の1になります。
負担調整措置
評価額が同じであっても、所在する地域によって税額に格差があることは、負担の公平の観点から問題があるので、この格差を是正するために設けられています。
土地の評価額が高騰しても、課税標準額の上昇がゆるやかになるため、税負担の上昇もゆるやかになります。
この制度は、負担水準(当該年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)によって次のようになります。
- 負担水準が高い場合は、税額を据置き、または、引き下げます。
- 負担水準が低い場合は、段階的に税額を引き上げます。
住宅用地
本来の課税標準額(A)(今年度の価格に住宅用地の特例を適用した額)に対して
前年度の課税標準額が(A)未満の場合
前年度の課税標準額+(A)×5%
(A)を上回る場合は、本来の課税標準額になります。
(A)の20%を下回る場合は、A×20%になります。
前年度の課税標準額が(A)以上の場合
本来の課税標準額になります。
商業地等
今年度の価格(B)に対して
前年度の課税標準額が(B)の60%以上70%以下の場合
前年度と同額になります。
前年度の課税標準額が(B)の60%未満の場合
前年度の課税標準額+(B)×5%(令和4年度に限り2.5%)
(B)の60%を上回る場合は、(B)×60%になります。
(B)の20%を下回る場合は、(B)×20%になります。
前年度の課税標準額がBの70%を超える場合
(B)×70%になります。
家屋に対する課税
使用されている資材・設備などを、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、部分別(屋根・外壁・内壁など)に算出して評価額が決定されます。
原則として課税標準額は評価額と同額になります。
家屋を新築・増築したとき
家屋が完成した後、担当者が現地調査を実施しますのでご協力ください。
- ご入居前の調査をご希望の方はスケジュールの調整を行いますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。
家屋の用途を変更したとき
店舗を住宅、住宅を事務所にといったように、改装等により家屋の用途を変更した場合、調査が必要となることがありますのでご連絡ください。
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、担当者が現地を確認しますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。
家屋については、毎年1月1日現在に存在する家屋の所有者に課税されますので、1月2日以降に取り壊しをした場合は、翌年の1月1日を賦課期日とする年度から課税されなくなります。
なお、住宅を取り壊したことで当該土地が住宅用地ではなくなった場合、住宅用地の特例が適用されなくなり、土地の固定資産税額が上がります。
新築住宅に対する減額
(1)減額される住宅要件
次の条件を両方とも満たしていることが必要です。
- 居住部分が家屋の2分の1以上
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
(2)減額される期間
- 一般の住宅は新築してから3年間(そのうち長期優良住宅は5年間)
- 3階建以上の中高層耐火住宅は新築してから5年間(そのうち長期優良住宅は7年間)
(3)減額される税額
住宅部分のうち床面積が1戸当たり120平方メートルを限度として、固定資産税額の2分の1が減額されます。
償却資産に対する課税
事業用に使用することができる機械設備や備品等の資産に対して、その取得価額に、国が定める減価率を乗じて評価額を決定します。
原則として課税標準額と評価額は同額になりますが、課税標準の特例の対象となる場合は、課税標準額が評価額よりも低くなります。
償却資産の申告
賦課期日現在に所有している資産の内容を、その年の1月31日までに申告してください。
電子申告(eLTAX)での申告
償却資産の申告にはeLTAXをご利用いただけます。
詳しくはeLTAX(エルタックス)地方税の電子申告をご利用くださいをご覧ください。
課税標準の特例>
償却資産の用途や種類により、課税標準額の特例の対象となる場合があります。対象となる償却資産は、法令により細かく決められていますので、詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。
固定資産税の減免
次のような固定資産に対しては、市長が必要があると認める場合、固定資産税の減免の対象となります。
- 生活保護を受給している人が所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 災害により損害を受けた固定資産
減免を受けるためには、納期限までに減免の申請をする必要がありますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。
お問合せ先
固定資産税係(土地・家屋)
電話: 0770-22-8108
関連リンク
市税の納期
![]() 土地及び建物の相続登記について《福井地方法務局》(外部サイト)
土地及び建物の相続登記について《福井地方法務局》(外部サイト)
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合,法務局において相続登記の手続が必要です。
詳しくは,法務局の窓口までお尋ねください。